
節分と言えば鬼だけど、あんまり怖い絵本は読みたくないなあ…
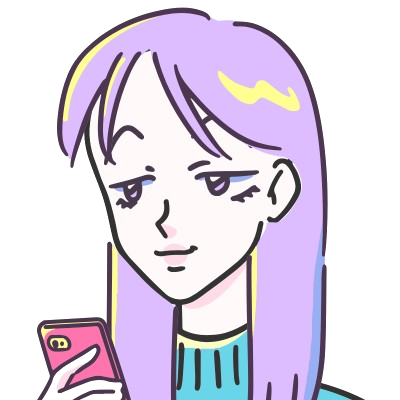
鬼というだけで怖がっちゃうポテトでも読める楽しいオニ絵本を集めました!
節分の読み聞かせにもおすすめです。
節分といえば鬼を払う行事ですよね。
鬼は昔話だけでなく、今の絵本にも多く登場するある意味人気者でもあります。
でもそもそも、鬼ってどういう存在なのか考えたことはありますか?
こんな方におすすめ
- 節分についての読み聞かせ絵本を探している
- 怖くない鬼の絵本が知りたい
- 節分について知ってみたい
節分についての基本
節分とは?
日本では節分といえば2月3日のイメージが強いですよね。
でも、実は節分って年に4回もあるんです。
春夏秋冬、それぞれの季節の始まりは二十四節気で立春・立夏・立秋・立冬と呼ばれています。
節分とはそれらの日の前日を指しているのです。
二十四節気は年ごとに日付が変わってしまうので、節分の日付も変わってしまうんですね。
その中でなぜ立春の節分が重きを置かれるのかといえば、旧暦では立春が新年の始まりだったから。

つまり、立春の節分は今でいう大晦日のような扱いだったんですね!
どうして豆まきをするの?
昔は、季節の変わり目には邪気が生じると信じられていたので、これを追い払うためだと言われています。
もともとは中国の宮中で行われていた“追儺”という鬼払いの行事が、日本でも取り入れられたようです。
この追儺には鬼払いは含まれていたものの、豆まきは含まれていませんでした。
追儺は平安時代には既に行われていたようですが、現在のように豆をまいて鬼を追い払う形となったのは室町時代からなのです。
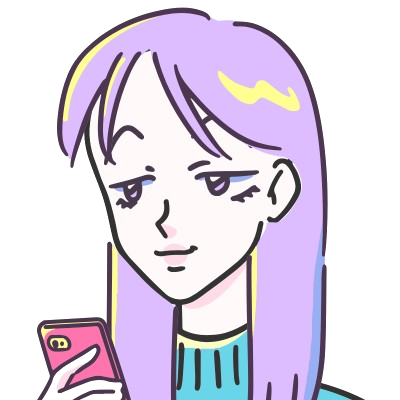
彬子女王がかつての宮中行事・節分について書かれたコラムが大変興味深いのでおすすめです!
節分に行われていることは?
各地の神社仏閣で節分祭・節分会が行われる
よくニュースにもなっている成田山新勝寺のように力士や有名人が豆まきをするところもあれば、京都の吉田神社のように古来の追儺式を行うところもあります。
「鬼は外、福は内」が一般的な掛け声も「鬼は内、福も内」というところもあれば、「鬼は内、福は外」なんてところも。
地域や神社仏閣によって様々な特色があり、昔から大切にされてきた行事なのだと伝わってきます。
一般家庭でも豆まきや恵方巻など
一般的な風習としては、「鬼は外、福は内」と言いながら炒り豆をまくこと、年齢の数だけ豆を食べることがメジャーですね。
そのほかにも玄関に柊鰯を飾ったり、護符を貼ったりするところも。
旧暦では年越しということもあり、年越し蕎麦ももともとはこの日に食べられていたそうですよ。
鰯を食べたり、恵方巻を食べたりする地域も。
恵方巻は関西の文化でしたが、今では全国的に展開されていますね。
鬼について
鬼といえば角が生えた、金棒を持った日本の妖怪をイメージします。
昔話でももちろん悪者として出てくることが多いですよね。
地獄で閻魔様の手先として働く鬼をイメージする方も多いと思います。
鬼は“おぬ”?
鬼…おに、という言葉の由来は「おぬ」、つまり隠であって姿の見えないものを指す言葉だという説もあります。
また、鬼という漢字の読みが「おに」に定着する前は鬼と書いて「もの」や「かみ」と読ませることもあったそうです。
この世ならざるもの、姿は見えないが恐ろしく超人的なもの。
それは今のニュアンスでも分かるような気がしますね。
鬼の子孫?
この令和の時代にも、鬼の子孫を自称している方々がいます。
鬼の夫婦と子ども5人が暮らしたという鬼伝説の里には「五鬼助」さんというその子どものうちの一人が祖先だという名字の方が。
つまり、鬼と呼ばれる人々は実在して、子孫を残していたのです。
人が鬼になったという伝説も各地にありますし、鬼として見なされ差別されてしまった人々もいたことでしょう。
一言で鬼といっても、様々なオニがいるのです。
節分に読みたい!たのしい鬼の絵本
ここでは節分の読み聞かせにぴったりな楽しいオニの絵本を紹介します。
おにはそと
豆まきで鬼たちは逃げだしますが、残された可愛いちび鬼は人間の子どもたちと仲良く遊びます。鬼の親分がちび鬼を連れ戻しに、よろいを着て来ますが、豆まきに降参。親分はちび鬼のお父さんでした。心が和む楽しい絵本。
金の星社「おにはそと」
鬼さんと友達になれる!
子ども園などでも豆まきはお馴染みの節分行事ですよね。
鬼を怖がってしまうお子さんにもおすすめな節分絵本がこちらです。
せなけいこさんの温かみのある貼り絵がまたかわいいんです。
ストーリーもほんわかで、きっと今年の豆まきが楽しみになっちゃうと思います。
ドオン!
突然、こうちゃんの上にオニの子ドンが落っこちてきました。こうちゃんはびっくりしてドン!と太鼓をたたきます。ドンもドン!ドン!と太鼓をたたきます。こうちゃんのおとうさんとおかあさんも、ドンちゃんのおとうさんとおかあさんも出てきて、ドンドコ太鼓たたきの合戦のはじまりです。人間とオニの仲間がどんどん集まってきて、お互い負けたくないから太鼓をたたきます。にぎやかな絵と文章で、太鼓の愉快なリズムが、爽快感を味わえます。
福音館書店「ドオン!」
リズムに合わせて太鼓合戦!
鬼との戦いシーンは数あれど、こんなに平和で楽しい戦いは他にありません!
こうちゃんとドンちゃんの太鼓合戦はみるみるうちにみんなを巻き込み、その音も激しくなっていきます。
長新太さんの絵がまた激しさを強調してとっても楽しい!
へぇこいたのだれだ?
「ぷ~う」あれれ、なんだかにおうぞ! おならしたのだれだ?
暗闇のなかでの子鬼3兄弟のおならをめぐるミステリー。掛け合いや、会話を特徴とする多くの絵本を生み出している作家、平田昌弘の会話が楽しい!
Amazon「へぇこいたのだれだ?」商品説明より
鬼の版画家、野村たかあきが、力をこめてユーモラスに彫った子鬼たちが、ぷぷぷっと笑える!
子どもたちが大好きな話!
読み聞かせ会などで絶対に盛り上がっちゃうであろうタイトルw
我が家も三姉弟なので、こういう話をよくするせいか笑える笑える!
おならの犯人は一体誰だったのか、ぜひ読んで確かめてみてください。
とほほ…でキュートな鬼さんたちの絵本
怖くない!どころかちょっと残念でキュートなオニの絵本を紹介します。
オニじゃないよ おにぎりだよ
おにぎり好きのオニたちが、人間の落としたおにぎりを拾って食べて大ショック!「ひどすぎる!こんなまずいおにぎりを食べてるなんて!」「俺達が本当のおにぎりのあじを教えてやる!」
Amazon「オニじゃないよ おにぎりだよ」商品説明より
マイタケ個人的にも大のお気に入り絵本
鬼=怖いというイメージのお子さんにこそ読んでいただきたい!
その概念を覆しちゃうくらい楽しすぎる絵本です。
読み聞かせする大人の方も思わず吹き出してしまうので初見ではやらない方がおすすめw
わたしも大のお気に入り、だいだいだいすきな絵本!!
まゆとおに
山姥の娘まゆは、ある日鬼に会います。鬼はまゆを煮て食べようとお湯を沸かしはじめます。まゆはそうとは知らず、薪の山を作ったり、かまどの石を積んだり、手伝います。その怪力に驚いた鬼も、鍋のお湯が沸くころには、もうすぐまゆを食べられるとにんまり。ところがお湯が沸くと、風呂を沸かしているとばかり思っているまゆは、「お先にどうぞ」と言うなり、鬼を鍋に放り込んでしまいます……。
福音館書店「まゆとおに」
鬼よりスゴイ山姥の娘まゆの怪力!
こちらもわたくしマイタケお気に入り絵本のひとつです。
このとっても怖い鬼の姿は、子どもたちが怖がる鬼そのもののイメージですよね。
でもそんな鬼さんは、マイペースなまゆに振り回されちゃうんです。
ピュアすぎるまゆの行動と空回りする鬼さんの行動のズレに笑っちゃいます。
まゆシリーズはどれも面白いのでおすすめ!
ソメコとオニ
五歳の女の子・ソメコはあそびざかり。オニにさらわれてもこわがるどころか、あそびのさいそく。こまりはてたオニは…。
岩崎書店「ソメコとオニ」
オニさんの手紙に笑っちゃう
こちらはオニが女の子をさらってしまうお話。
でもその女の子・ソメコはオニを怖がる素振りはなく、遊び相手にしちゃうんです。
計画が狂ってしまったオニの行動がおかしくて!
最後の手紙には思わずクスクス笑ってしまいます。
嫌われ者の哀愁…せつない鬼の絵本
どうしても恐れられてしまう存在だからこその孤独や哀愁も。
ちょっぴりせつなくなっちゃうオニの絵本です。
島ひきおに
人間と暮らしたいと住みかの島をひっぱって鬼が村へやってきましたが、こわがって誰も遊びません。鬼は再び島をひいて歩きます。
偕成社「島ひきおに」
鬼から歩み寄っても受け入れられない…
鬼の方から人間たちと仲良くなりたいと文字通りに歩み寄ってくるのですが、人間から見たらえらいこっちゃですよね。
でも怖がり恐れる人間たちの方が、見た目は恐ろしい鬼よりも怖いのかも…
偏見についても考えさせられるお話です。
おにたのぼうし
節分の夜、豆まきの音がしない一けん家にとびこんだおにのおにたは、病気の母を看護する少女に出会います。
Amazon「おにたのぼうし」商品説明より
鬼だっていろいろ、人間だっていろいろ
鬼だから…人間だから…そんなふうに判断してしまうことの危うさがよく伝わる切ないお話。
優しくない人間もいるように、優しい鬼もいるのかもしれない。
大人にも心に響く絵本です。
ないたあかおに
村人となかよくしたい赤おにと、そのねがいをかなえてやろうと、自分が悪者になる青おに。おに同士の友情を感動的に描きます。
偕成社「ないたあかおに」
読むたびに感想が変わる
切ない鬼のお話といえば真っ先にこれを思い浮かべる方も多いであろうロングセラーです。
子どものころ、小学生になってから、思春期、大人…その時々できっと感想が変わってくると思います。
あかおにに感情移入するのか、あおおにの気持ちを慮るのか、人間側の気持ちを読み取るのか。
一度は読んでみてほしい、いろいろ考えさせられる絵本です。
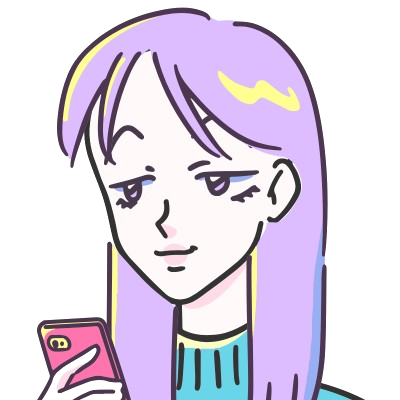
鬼はいちばん身近な妖怪だからこそ、いろいろな題材になっています。
豆まきや恵方巻だけでなく、いろんな風習を知っておきたいですね!

日本の芸術文化を学べる絵本も読んでみませんか?
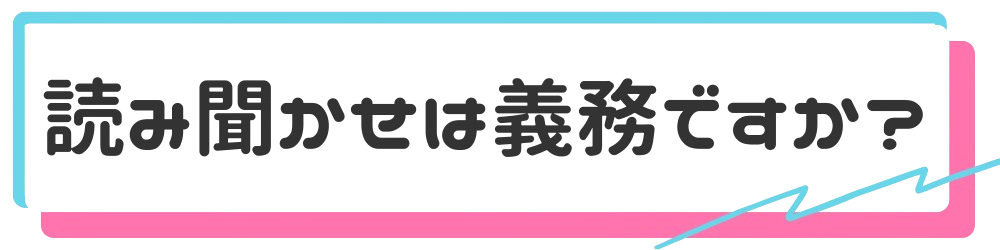
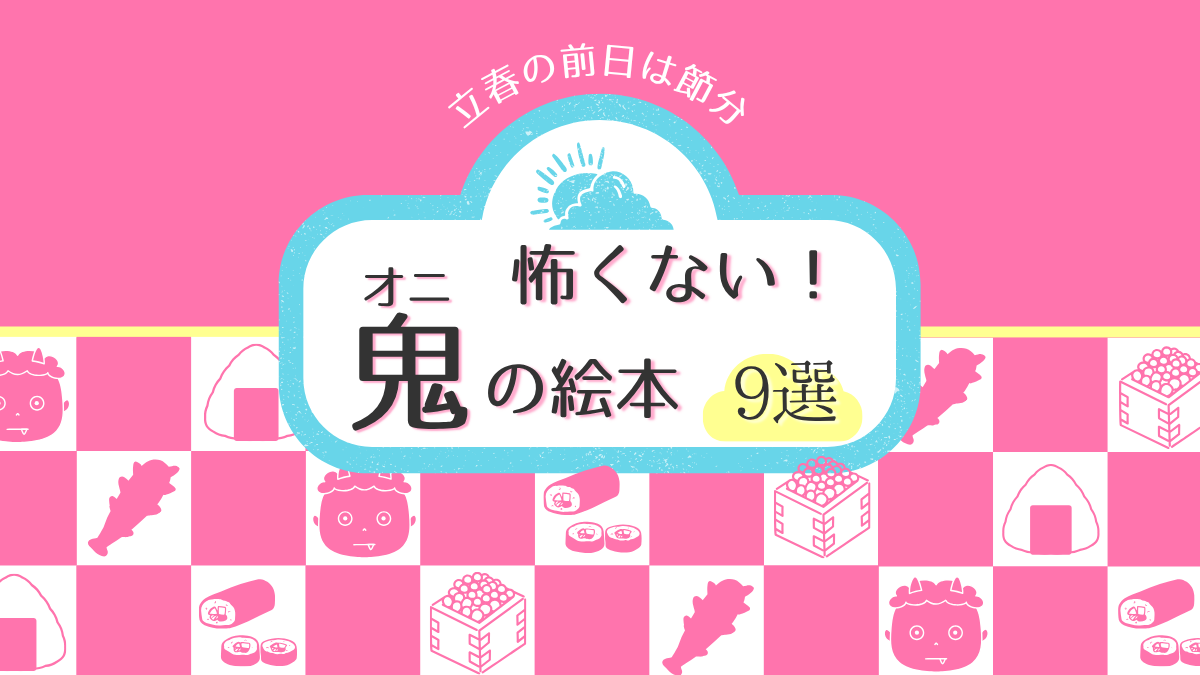











コメント